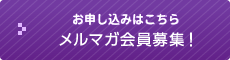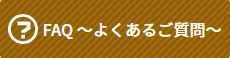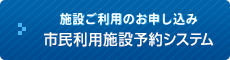公開日 2025年09月15日

2年に一度開催される横浜芝山漆器研究会の展示会です。
今回は横浜市技能文化会館と共催し、匠プラザで開催いたします。
会館の収蔵品はもとより、金子皓彦コレクションから著名な作品と会員一同の作品を展示いたします。
また、横浜芝山漆器研究会会員が製作した額絵、インテリア小物品等、数々の作品を展示販売いたします。
皆様お誘いあわせの上お越しください。
開催概要
| 期 間 |
2025年10月10日(金) ~19日(日) |
| 時 間 |
午前10時~午後5時(最終日は12時迄) |
| 会 場 |
横浜市技能文化会館1階 匠プラザ |
| 入場料 | 無料 |
| 主 催 |
横浜芝山漆器研究会 |
| 共 催 | 横浜市技能文化会館 |
| 後 援 |
横浜市経済局 全国税理士共栄会文化財団 一般社団法人日本漆工協会 |
| 開催チラシ | 令和7年横浜芝山漆器展チラシ[PDF:2.3MB] |

横浜芝山漆器の歴史と現状
安永年間(1775年頃)上総の国(千葉県)、現在の成田空港近くの芝山村に住んでいた大野木仙蔵という人が芝山象嵌の創始者と言われています。その後、同氏は芝山仙蔵と改名し、江戸に出て芝山象嵌を広めました。江戸を中心に受け継がれてきたこの芝山象嵌は、1859年の横浜開港によって大きな転換期を迎えました。
新しく開かれた港町を行き交う外国貿易商たちは、芝山象嵌の繊細美あふれる独自の技法を高く評価し自国に持ち帰りました。そして政府の殖産興業策と相まって海外から多くの注文が来るようになりました。そのため、多くの職人が横浜に移住するようになり、芝山象嵌の生産が本格的に始まりました。特に1893年シカゴ万国博覧会に出品された「真珠貝花紋小箱」が入賞を果たすと、その技法は芝山象嵌に携わる職人たちに大きな影響を与え、次第に芝山象嵌から異なる道を歩み始め、横浜独特の芝山象嵌が形成されるようになりました。
しかし、明治、大正と隆盛を誇った芝山漆器も、関東大震災や横浜大空襲による町の崩壊、それに伴う職人たちの離散などの理由から、残念ながら現在ではこの伝統技法の継承者も少なくなってしまいました。今回の芝山漆器展におきましては、横浜開港と共に歩んできた芝山漆器のすばらしさを、改めてみなさまに広くご紹介できれば喜ばしく思います。
横浜芝山漆器研究会
関連イベント
横浜芝山漆器研究会見学会
研究会の活動の様子をご見学いただけます。
| 日 時 | 2025年10月14日(火) 午後2時~3時 |
| 会 場 | 横浜市技能文化会館6階 602工芸研修室 |
| 申 込 |
不要 |
展示品
●横浜市技能文化会館収蔵

●神奈川県立歴史博物館寄託 金子コレクション

●研究会会員の作品

その他展示品多数ございます。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード