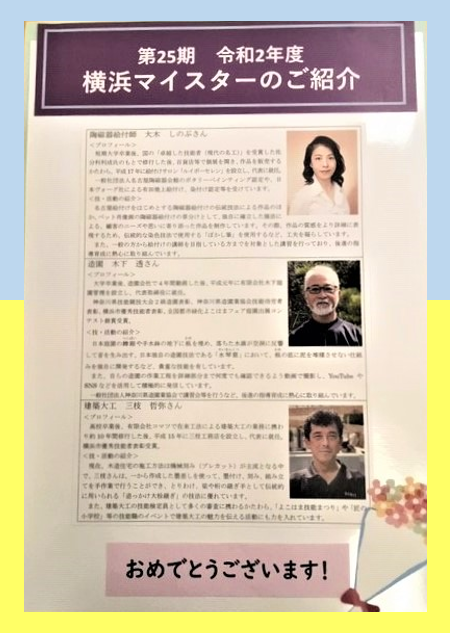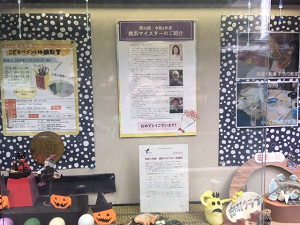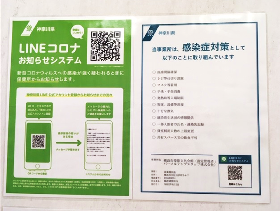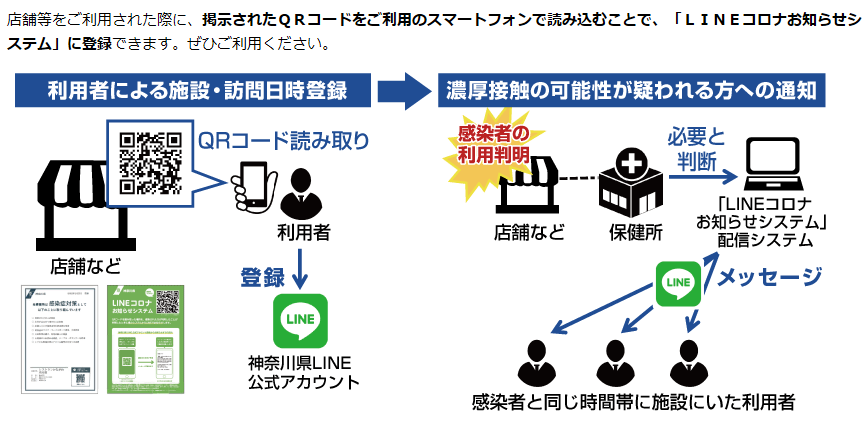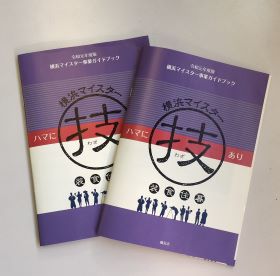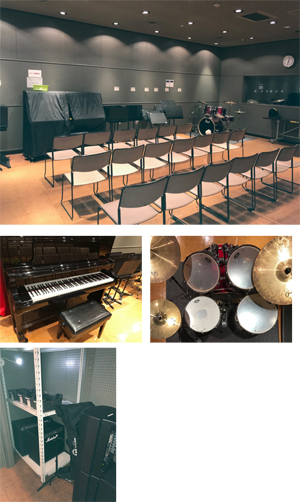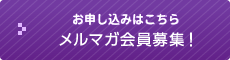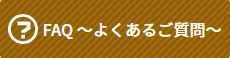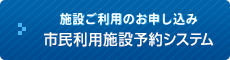技文便り「館長より」□■□技文便り□■□”Vol.129”館長より 2020/11/92020年11月09日
寒くなり始めのこの時期は、毎日の服装に悩みますが、
薄手のコートやスカーフ、ストールなどが活躍し出し、好きな季節です。
そして、「技文手ぬぐいマスク」も暖かく感じ出しました。(笑)
昨年の11月は馬車道マルシェで張り切っていました。
給湯器の入替工事により、各階の給湯室でお湯が使えるようになりました。
日常使用しているPCが、Win10に変わり四苦八苦し(苦笑)
令和元年が暮れていきました。
2階の女子トイレは念願の洋式化となり、エレベーター工事も始まりました。
中学生のインターンを受け入れたり、リーフレットを作り変えたり、、、と
していたところ、2月からは「コロナウイルス」という名称が聞こえ始めました。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止」という言葉もどれだけ使用したかわかりません。
再開してからは、「**を開始」「**を導入」「**に変更」が多く、
コロナウイルス一色であったものの、「開始(新しいこと)と変化」も多くありました。
「新しいこと」は、戸惑いもあり、面倒に感じることもあります。
しかしながら、何か「発見」がありましたし、始めるための準備として調べたり、考えたりしたことも、
会館全体に足場を組み、すっぽりと仮囲いをします。
大きな建物ゆえ、足場組みに1か月程度かかる予定です。
その間、音や振動等でご迷惑をおかけすると思いますが、ご理解をお願いいたします。
また、工事の影響で、2月~3月は、一部のスペースで暖房が使用できません。
戦々恐々としているのですが、仮囲い=ビニールハウス?とも考えられ、
もしかしたら意外と暖かいのかもしれない!とも思っています(苦笑)
また、風邪や感染症の季節本番になってまいりますので、
引き続き「手洗い」「手指消毒」「マスク着用」をお願いいたします。
くれぐれもご自愛のうえ、お過ごしくださいませ。
横浜市技能文化会館館長 山口亜紀