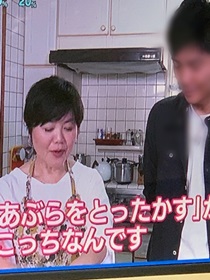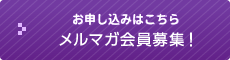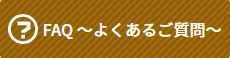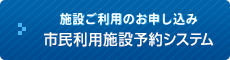花冷えの3月23日(土)に、初めて洋裁クラブ作品発表会を開催しました。
はじめに、洋裁組合の山本会長より、組合の歴史や技能検定についてのお話を伺いました。
2級を取得するには「ブラウス10枚は作ってみないと!」などのお話を聴き、
驚きながらも参加者は製作意欲が湧いているようでした。
続いて、作品発表のミニファッションショーを行いました。
皆さんの思いがこもった作品達は、とてもよくお似合いです。
◆テーラードカラーと肩のラインがキリッと決まったオーバーブラウス
◆道行コートはカフスがポイントの素敵な羽織ものに
◆花柄のコートドレスに、手製の刺繍バッグを合わせたロマンティックな装い
◆シックな紬のジャケットには赤いイヤリングでモダンな着こなし
◆小花の刺繍生地のチュニックは、丁寧な仕上げでお似合いに
◆別珍のベストスーツは、思い入れの玉縁ボタンホールで贅沢に仕上げ
◆和布のカジュアルフレアーコートは軽やかに
各自の作品を観賞し合い、良かった点や苦労した点などを披露し、講師の皆さんから講評いただきました。
全員で記念撮影もし、ホッとしたところで、お茶を飲みながら、洋裁クラブの様子をスライドで振り返りました。
最後に参加者の感想をご紹介します。
◇作品に自信がなかったけれど、参加してみて良かった。愉しかった。
◇ファッションショーに抵抗があったけれど、参加したら楽しく、製作意欲が湧き、元気が出てきました!
◇皆さんの作品が刺激になり、また新たな作品づくりに挑戦したくなりました!
◇11ヶ月かかったけれど、自分の作りたかった玉縁ボタンホールができて嬉しかった。
◇母の思い出の道行コートが素敵なコートに生まれ変わりました。
◇ワイドパンツ講座から、講師の指導が素晴らしく洋裁クラブも続けて受講しました。
洋裁をすることで、ものづくりをこれからも楽しみたいと思っています。
◇きりびつけは、料理で言えば下ごしらえ。大変だけど後から楽になることなど、細かい技術を学べて嬉しいです。
これからも好みの服を好きな生地で作りたい!
作品発表会では、皆さん、ますます製作意欲が高まり、担当者としてとても嬉しく思いました。
ご参加の皆様、講師の皆様、ありがとうございました。
4月からは、基礎の洋裁、応用の洋裁として土日に開講いたします。
皆さまのご参加をお待ちしています